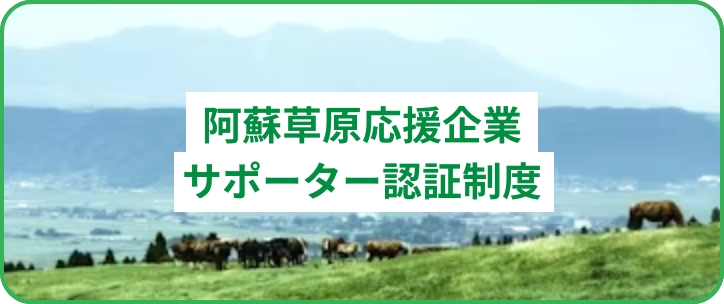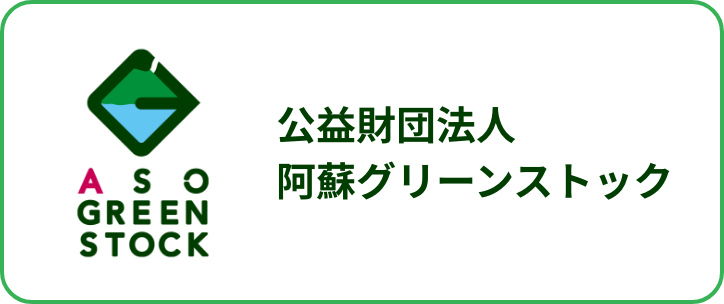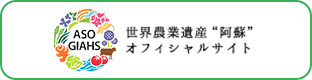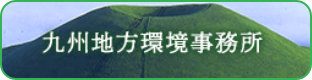岩本和也(いわもとかずや)さん
【PROFILE】
1958年生まれ、熊本市在住。20歳の時に半導体関連会社から消防士へ転向。ライフワーク的にボランティア活動に邁進する中で、阿蘇の草原と出会う。在職中から野焼き支援ボランティアの活動を続け、定年退職後は電気設備会社、農事組合法人を経て行政書士の道へ。持ち前の行動力で変幻自在に人生を楽しむ。令和元年より野焼き支援ボランティアの会の代表として約1060名のボランティアを取りまとめる立場に。野焼き支援ボランティア創設当初からの会員で、2024年に25年目を迎えた。
「自分の時間は、社会への恩返しに使いたい」
野焼き支援ボランティアの代表として歩んだ25年の軌跡。
野焼き支援ボランティアの代表・岩本和也(いわもとかずや)さんが、“草原”の存在を意識したのは、現役の消防士として働いていた1997年の39歳の頃。朝8時半までの勤務を終えた岩本さんがおもむろに新聞を開くと、視界に飛び込んできた「草原募金募集」の文字。フットワークの軽い岩本さんは、その足で草原募金の受付会場の新聞社を訪れます。
「少額ですが募金をさせていただいた後に、「野焼きのボランティアも募集したらどうでしょうか」、と提案しました」と岩本さん。実は、当時から地元のいくつかのまちづくりのボランティア活動に参加する中で、“ボランティア”という立場が担う役割に可能性を感じていたそうです。ボランティアという立場でありながら、時にはCADや測量機器を使って計画書を作成し、作業の許可申請まで自身で行っていたという岩本さん。CAD?測量‥?一般的なボランティアのイメージをはるかに超えた仕事ぶりに驚く筆者に岩本さんは飄々と続けます。
「消防士は火事が起きた現場の記録を作成する際に、図面を引くことがあるんですね。細かい修正があった時は、やはりCADを使った方が綺麗に仕上がるので独学で覚えました。職員にもソフトの使い方をよく教えていましたよ」。
まもなく野焼き支援ボランティアの募集開始が始まり、それから25年たった今、会員Noは2800を超えていますが、岩本さんの会員Noは、一桁のNo.4。消防士だった頃から野焼き支援ボランティアの活動を始めて25年。さらに、リーダーに就任して23年、代表に就任して5年。野焼き支援ボランティアの中でも、責任のある役割を長く続けて来た理由はなんだったのでしょうか。
「誰かがやらなければ、草原も、ボランティア活動も無くなってしまうでしょう。学生時代の私は、学校内の体力測定でも1位2位を競うほど丈夫な体に恵まれました。ボランティアに来られる方は、年齢や体力などさまざまな環境の方がいらっしゃる中で、体も丈夫で時間も比較的調整しやすく、消防という防災と安全管理の知識を持つ自分がボランティアリーダーを引き受けない理由はないと思ってきました。現在は“代表”という立場でリーダーシップがあると思われがちですが、どちらかといえば頭を柔らかくして様々な意見に耳を傾ける、傾聴することを心掛けている調整型の人間です」。
何事もできるだけ断らず、多くの人の声を聴くことがモットーだという岩本さん。とはいえ、野焼き支援ボランティアを続けるなかで、挫けそうになったこともあったはずです。
「しんどかったのはボランティアを初めて12回目の春ですね。親しくしていたボランティアリーダーさんの死亡事故が起きた時です。私は現場から10キロほど離れた場所で作業をしていました。11時半ごろに終わって事故の報せを受け、事務所で緊急会議を開きました。事故をきっかけに『安全管理対策特別委員会』を立ち上げ、ボランティアとしての姿勢を1から見直しました。あの時は消防士として勤務していましたが、有給休暇が無くなるまで何度も何度も会議を重ねましたね。安全管理と責任の問題は必ずセットです。でも、誰かがやらないと大切なものは守れません。そこの敷居をいかに低くしていくかということは常々考えています」。
岩本さんや野焼き支援ボランティアのリーダーさん、事務局を担う「阿蘇グリーンストック」が一体となり、徹底した安全管理に取り組んできた結果、今や全国から視察が訪れるほどの団体へと成長を遂げています。想いあるボランティアさんたちの存在とそれを支える事務局は、どちらも欠くことのできない車の両輪のような存在なのです。
ボランティアは、楽しまなければ続かないとはいえ、野焼きは責任の重い仕事です。その責任をいかに楽しむか。それはまるで子育てのように難しいテーマです。そこに挑戦し続ける岩本さんが、ボランティア活動に意識を向けたきっかけはなんだったのでしょうか。
「私が半導体関連の会社に入社した頃は、半導体産業の全盛期で深夜残業、早出出勤の毎日でした。精神的にも体力的にもハードで、自分の立ち位置を振り返る余裕もない日々を2年間過ごした後に、消防士になったという経緯があります。そこで改めて1日の時間の配分を考えてみると、寝る時間が1/3、働く時間1/3、残りが自分の時間になりますよね。当たり前ですが自分の時間をどう過ごすかは、自分の裁量次第です。だったらその時間を社会に対する恩返しのために使いたいと思いました。それが20歳の時です。実際にボランティア活動を始めたのは30代からですが、今でもその思いに変わりはありません。」
5年前に定年退職を迎え、1年間電気設備の会社に勤め、電気工事施工管理技士として国道57号線北側復旧ルートの工事に従事。その後農事組合法人事務局長を経て、今は行政書士として時間に縛られない働き方をしているという岩本さん。やってみたいことと、世の中の役に立つこと、その両方が融合し、岩本さんの中に絶えず湧き起こっていることが不思議です。野焼き支援ボランティアもまた、その一つです。
「野焼きを始めた当初は、地元の方から『ほんとにボランティア(無償)で参加してると?』とかなり珍しがられましたが、作業の合間に地元の方に阿蘇の話、草原の話を聞く時間がとても楽しみでした(笑)。私もボランティアの一人ではありますけど、温泉券などわずかな振る舞いでも、何時間もかけて遠方から思いを寄せて阿蘇にやって来られる皆さんは本当にすごいなぁといつも思います。初心者研修に参加されるだけでもすごいことだと思うんですよ。そこから野焼きの現場に参加される行動力と熱量は、さらにすごいこと。そういうエネルギーに満ちた方が1000名以上も集っていること自体、素晴らしいことだと思います。おそらくここで出会う皆さんは、他でも色々なことを学んでいかれる方なんだろうなと思っています。」
野焼き支援ボランティアを25年続けていても、その日の風を読むことはまだまだ難しいという岩本さん。特に野焼きの前段階である輪地切りや輪地焼きの作業はほとんど手作業になるため、それをやってのける人の力に毎回感動しているとか。
「私は職業柄、火消しの原点に立ち返るために、野焼きを続けている部分もありますが、多くの方はそうではありません。時折『ここまであなたを駆り立てるものは何ですか?』と尋ねます。すると多くの方が『阿蘇が好きだから』と答えられます。そこでおっしゃる“好き”も人それぞれ。いろんな阿蘇に対する“好き”があるので、深いなぁと思います。自分の“好き”を振り返ってみると、阿蘇は景色も人もいい。ボランティアさんも個性的で一人ひとりが興味深いですし、行き帰りの道中も好きです。天気が微妙な時もありますが、毎回景色が違いますからね。野焼きの日に雲海が出そうな時は、カメラを持って早く出かけますし、勤めていた時も早朝4時半に家を出発して、雲海を見て8時に出勤してました。いやぁ、やっぱり阿蘇の魅力は一言ではなかなか言い切れませんね(笑)」。
野焼き支援ボランティアの活動を通じて出会った阿蘇は、岩本さんにとってひときわ特別な場所であり、わが子のように愛おしい存在なのです。
あなたも野焼き支援ボランティアに参加しませんか?
阿蘇の草原は長い間「採草」「放牧」「野焼き」を継続的に行うことで維持されてきました。野焼きは春先に原野の枯草を焼き払うことで草原を管理する手法です。水源涵養や生物多様性など多くの恵みをもたらす草原の維持には欠かせない取り組みです。
実は、そんな野焼きは多くの準備や人手を必要とするとても大変な作業です。担い手不足により地元だけで野焼きをできなくなったところも多くあります。そのようなところに支援に入り、地元の方と協働で野焼きを行うのが「野焼き支援ボランティア」です。
野焼き支援ボランティアは阿蘇の貴重な草原を残すために欠かせない存在であり、毎年延べ2,000名以上の方が活動に参加しています。ただし、野焼きは危険を伴う作業であり、参加するには相応の知識を身に着け、ボランティアのルールを守る必要があります。
「野焼き支援ボランティア初心者研修会」では、野焼きにおける安全管理、ボランティア活動時のルール、活動参加の要領などについて学ぶことができます。
「阿蘇の草原を守りたい!」「草原や野焼きに興味がある!」という方はぜひお申し込みください!