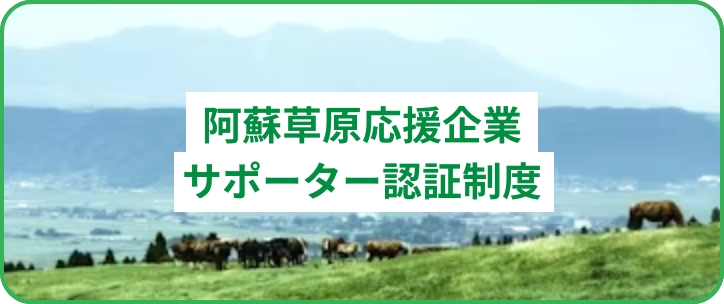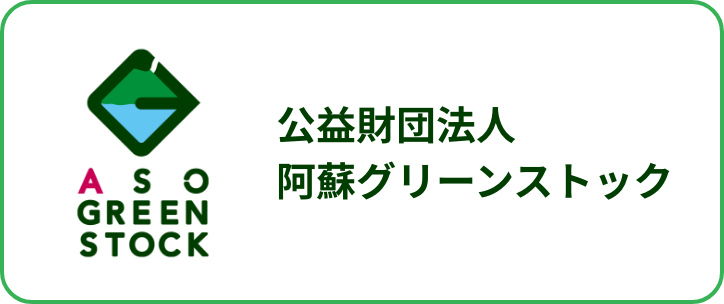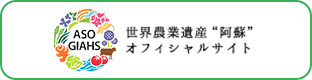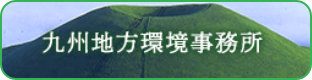農学博士 高橋 佳孝さん(たかはしよしたか)
【PROFILE】
1954年、小倉市生まれ。「阿蘇草原再生協議会」会長。「全国草原再生ネットワーク」会長。中国地方や阿蘇を中心に、日本の草原保全や管理に関わってきたスペシャリスト。生態系や農畜産業、文化景観など多様な視点で草原研究や調査を行う。
草原の伝統にまなぶ、
持続可能な未来の形。
「野焼きは、無形文化財に値する技術です」。やわらかな語り口で、確信的な言葉を話す高橋佳孝(たかはしよしたか)先生。2005年に発足した「阿蘇草原再生協議会」の会長として、阿蘇の草原を見守り続けるとともに、畜産、文化、生態系などさまざまな視点で研究を続けられてきた草原の第一人者です。長年、草原に寄り添ってきた研究者に、改めて草原の歴史や草原の持つ可能性について語っていただきました。
ー2023年度は、累計2200人以上の方が野焼き支援ボランティアとして全国から参加されたそうですね。そもそも野焼き支援ボランティアとは、どのような作業をするのでしょうか?
「野焼き支援ボランティア講習会」に参加した後、野焼きの現場に加わっていただきます。基本的には地元の方が火を付けた後に行う火消しの作業がメインとなります。
ー野焼きの現場が抱える課題を教えてください。
最大の課題は、野焼きの要となる “火引き” 技術の後継者不足です。火引きは、気象条件や地形の特性を考慮しながら草原に火を放つ重要な役割で、これまでは阿蘇の地元の人々やUターンで阿蘇に戻ってきた方がその技術を継承してきました。しかし、現在では火引きの後継者となりうる人材そのものが減っています。

ーそうした地域の現状を打開する対策はありますか?
南阿蘇村では2024年から「野焼きのプロ人材」認定制度を設けました。地元以外の人でも火引きの技術を学び、継承できるように、野焼きの専門家集団を育成する取り組みです。とはいえ、火引きは高度な技術であり、知識や経験の積み重ねが不可欠です。時間はかかるとは思いますが、少しずつ後継者を育成していく必要があります。
ーライフスタイルが変化した今、地元の方々にとって野焼きとは、どのような存在なのでしょうか。
阿蘇はもともと畜産や農業が盛んな地域で、草原は暮らしに欠かせない資源でした。しかし、近年のライフスタイルの変化により、草資源が必要でなくなり、草原維持の必要性も減ってきています。今では地元の方々は、農業以外の仕事に従事することも多く、それぞれの仕事を持ちながら休日を使って野焼きに参加しています。 阿蘇に暮らす人々は今でも草原の恩恵を受けて暮らしていることに変わりはありませんが、草という資源が暮らしの必需品ではなくなったことで、野焼きを続ける意義を見いだしにくいという側面もあります。
ーそうした状況の中でも草原の現場で前向きな動きはありますか?
野焼きにおける課題には担い手不足もありますが、重要なのは安全管理です。2023年には、野焼きにおける森林火災などの被害に対応する賠償保険の仕組みがようやくできました。これにより、「安心して野焼きができるシステムさえあれば、自分たちは続けます」という地元の方々の思いを支えることができるようになりました。このような取り組みを継続し、野焼きの伝統を守っていくことが重要です。
ー暮らしの糧を得るための野焼きから、草原そのものを維持するための野焼きへ、関わり方が変化しているんですね。
人が野焼きを行う目的は時代とともに変わっても、草原のあり方そのものは1万年以上前から変わっていません。そこに蓄積されている人と自然の関わりそのものが草原の価値であり、それが持続可能なところが草原の最大の魅力です。 人々が野焼きを続ける限り、“草”という恩恵を毎年享受し続けることができます。こうして千年、一万年と続いてきたのです。
ー脈々と受け継がれてきた草原に、日本全体としてどのような学びを得ることができるのでしょうか。
将来を見据え、農業や畜産、茅葺き屋根の文化、観光資源の活用、さらには生物多様性の保全といった国家的なプロジェクトを考える際にも、草原のシステムは大いに参考になります。地域の人が守り続けて来た草原のシステムは、“伝統”でありながらいまだ解明されていないことも多いもの。だからこそ、草原の維持と継承を大前提として学び続けることが必要です。
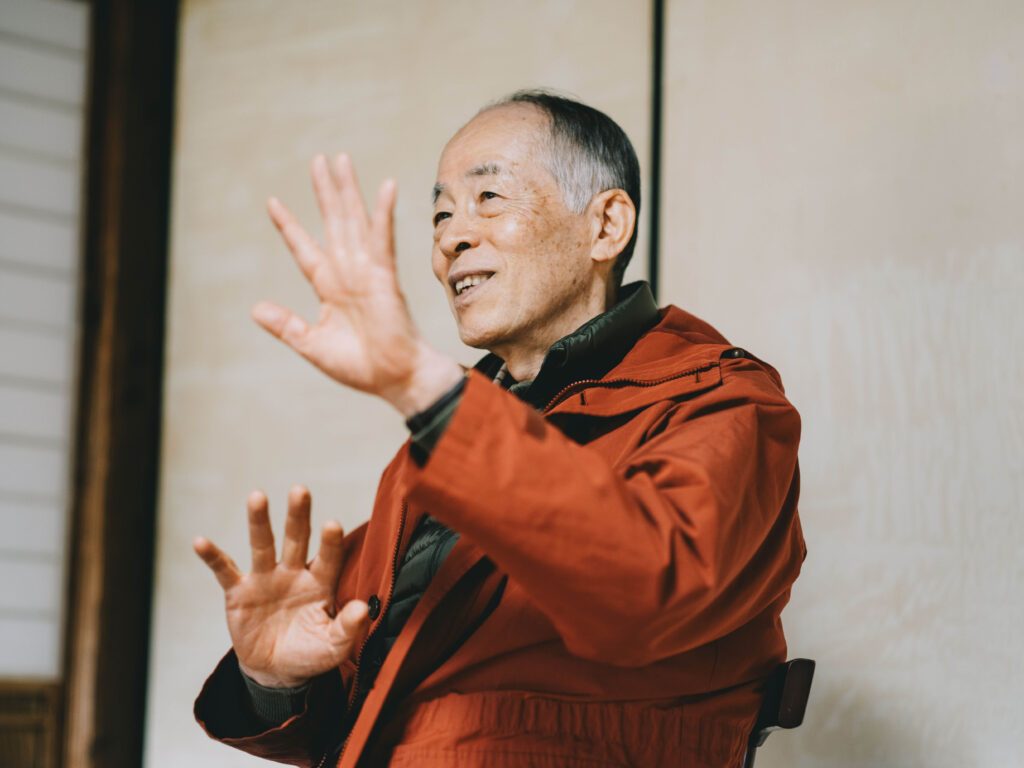
ーそうした重要な鍵を握っているにも関わらず、全国の草原の面積は加速度的に減少しています。草原の価値や重要性が認知されにくいのはなぜでしょうか?
“草原”というものがそもそも人々にとって明確な “対象”として認識されにくいからでしょうね。農地や林地とは異なり、草原はその中間にある移行帯とみなされがちです。肥料の材料や家畜の飼料を得る場所であっても、農産物や林産物を生産する場ではないため、その価値が見落とされやすいのです。
現在、環境省が草原の維持・保全を担当していますが、かつては農林水産省なのか林野庁なのか、国の行政の中でも管轄が曖昧な時期がありました。
そもそも草原は、人の手を加えなければ森林に遷移してしまいます。単なる「空き地」とみなされ開発が進むと、一瞬で姿を消してしまう脆弱な存在でもあります。こうした背景から、草原がもつ価値を十分認識されることもなく、時代の流れの中で草原が全国から姿を消しつつある、というのが現状です。
ー世界的に見ても草原は日本と同じような状況にあるのでしょうか。
環境問題の視点抜きにして、農業をはじめとする産業を語ることは、世界的にもむずかしい状況にあります。例えばヨーロッパでは、地球温暖化対策の視点から、土壌や植生への炭素の隔離を増加させる農業の実践が推奨されており、これを“カーボンファーミング”と呼びます。その中でも、耕さず炭素を放出しない農業が注目されています。実は、草原は1万年以上にわたり、この持続可能な農業の形を実証してきました。こうした世界的な視点でみても、人類が草原から学ぶべきところは多いでしょう。
ー環境問題に配慮した先進的な農業の取り組みが、すでに草原の歴史の中で実証されているということは、非常に興味深いですね。
例えば、“草原に杉を植えると水が枯れる”と地元の先輩方はおっしゃいます。これには長年の経験に基づく根拠があるはずだと思います。地元の人に受け継がれてきた言葉を、近代的な知識だけで評価してしまうと、こうした知恵を見落としてしまいがちです。私たち研究者の役割は、地元の方の言葉によく耳を傾け、それを科学的に根拠づけることです。その連携が今、ようやく叶いつつあるのかもしれません。
振り返ってみると、人間は失敗を重ねながら意思決定を繰り返し、現代の社会を築いてきました。地元の人たちも、農業技術や生活の知恵においてたくさんの失敗をしてきているはずです。その中で淘汰されながら今に至っているわけですから、それが一番正しいやり方なのではないかと思います。
阿蘇では縄文時代から野焼きが行われていたことが確認されています。時代ごとに野焼きの目的が変化しても、なぜ今も野焼きが続いているのか。その答えこそが、持続可能な未来を生き抜くための鍵になるのではないでしょうか。
[後編に続く]